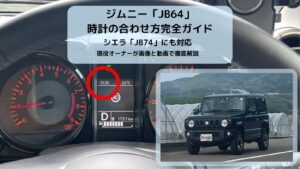「ジムニーの後部座席って、乗り降りしにくいってホント?」
結論から言うと、“ちょっと面倒だけど、慣れと工夫で快適に使える”のがJB64ジムニーの後部座席です。
実際に乗っている筆者や多くのオーナーの声を元に、この記事では
✅ 乗り降りが不便と感じる理由とその対策
✅ 子ども・高齢者でもラクに使える工夫
✅ 「買って後悔しない?」という不安を解消する実例
まで、まるごと徹底解説します。
購入前に知っておきたい“リアルな使い勝手”と“快適にするアイテム”も紹介しているので、
家族で使う予定の方や、乗降性が気になる方はぜひ最後まで読んでみてください!
【この記事で分かること】
✅ 3ドア構造による後部座席の乗り降りの流れと手順
✅ 狭さや使いづらさに対するリアルな使用感と工夫のしかた
✅ サイドステップやグリップなど快適性を高める補助アイテムの紹介
✅ 後部座席のリクライニングや乗り心地の改善方法とカスタム例
JB64ジムニーの後部座席、正直どうなの?
JB64ジムニーは、そのタフで個性的なデザインと走破性の高さで多くのファンを魅了しています。
一方で、「後部座席って実際どうなの?」「狭そうだけど大丈夫?」といった疑問の声も多く、購入を検討している方や家族での利用を考えている方にとっては、気になるポイントのひとつでしょう。
このセクションでは、ジムニーの後部座席について「実際にどう感じるか?」を、リアルな使用感とデータの両面から丁寧に解説していきます。
「狭い」「乗りにくい」は本当?まずはリアルな印象から
ジムニーの後部座席について、よく耳にするのが「狭そう」「乗りにくそう」といった声です。
実際に使ってみると、確かにセダンやミニバンのような広さは期待できません。特に大人が長時間座ると、足元や背もたれの角度に窮屈さを感じることがあります。
また、3ドア仕様のため後部座席へのアクセスは前席を倒してからとなり、乗り降りには一手間必要です。とくに女性やお子さま、高齢の方にはややハードルが高く感じる場面もあるでしょう。
しかしながら、「狭い=使えない」というわけではありません。日常の短距離移動や、非常時の4人乗車には充分に対応できる設計です。
「普段は2人乗り+荷室活用、必要に応じて後部座席を使う」というスタイルが現実的かもしれません。
3ドアゆえの宿命|乗降性と実用性はどうなの?
ジムニーが採用している3ドアボディは、悪路走破性を高めるためのショートホイールベース設計によるもの。これにより取り回しやすさやオフロード性能が優れる反面、後部座席の乗降性には制約が生まれています。
具体的には、後部座席にアクセスするには
1. 助手席側のレバーを引いてシートを前に倒す
2. スライドさせて通路を確保
3. 足元を気にしながら乗り込む
という手順が必要になります。これは慣れればそこまで苦ではありませんが、スムーズさに欠けるのは否めません。急いでいるときや、狭い駐車場では少々面倒に感じることもあります。
ただし、3ドアであること自体がジムニーの「味」でもあります。趣味性の高い車であるからこそ、ある程度の使いづらさも受け入れて楽しむというユーザーも少なくありません。
ジムニー後部座席の「広さ」「高さ」「快適性」を数値で比較
実際の寸法を見てみると、JB64ジムニーの後部座席スペースは以下の通りです(※スズキ公式資料などをもとに集計):
| 項目 | 数値(概算) |
|---|---|
| 室内長さ | 約1,795mm |
| 室内幅 | 約1,300mm |
| 室内高さ | 約1,200mm |
| 足元スペース(後席) | 約60〜70cm(前席の位置により変動) |
※上記は目安数値で、実際の使用感とは若干異なる場合があります。
数値で見ると、軽自動車としては標準的〜ややコンパクト寄りのサイズ感です。
特に足元スペースは、前席との兼ね合いに大きく左右されるため、長身のドライバーが運転席を後ろに下げていると、後部座席の足元がかなりタイトになります。
また、背もたれの角度が比較的立ち気味のため、「姿勢が固定されやすい」と感じる方もいるかもしれません。筆者が所有するジムニーJB64(2023年式)は、リクライニングできますが、正直「立ち気味」です。お世辞にも後部座席は「居住性が良い」とはいえません。
以上のように、JB64ジムニーの後部座席は、確かに「乗りにくさ」や「窮屈さ」といった要素はありますが、それらを理解したうえで「ジムニーというクルマの特性」として楽しめるかどうかがポイントです。
次のセクションでは、こうした不安にどう向き合い、どう工夫すれば良いのかをさらに詳しく見ていきましょう。
JB64ジムニー後部座席の乗り降りが不安な人へ|結論から言うと…
ジムニーの購入を検討している方の中には、「後部座席って、やっぱり乗り降りしづらいのでは?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
特に、初めて3ドア車に触れる人にとっては、「後席へのアクセスの手間」や「狭さ」に戸惑うかもしれません。
でも、ご安心ください。結論から言えば、確かに最初は少し面倒に感じるかもしれませんが、慣れと工夫次第で十分に快適に使えるようになります。
ここでは、そう感じる理由や共通の悩み、そして逆に「意外とラクだった」という声もあわせてご紹介します。
まず結論:乗り降りは“ちょっと面倒”、でも“慣れと工夫”で解決
ジムニーの後部座席は、助手席を一度倒してからでないと乗り込めないという構造になっています。これは3ドア車の特性によるもので、セダンやミニバンのようなスライドドアとは違い「ひと手間多い」のが事実です。
具体的な流れは以下の通りです:
1. 助手席側のレバーを引く
2. シートを前に倒し、スライドさせて通路を作る
3. 足元を気にしながら後部座席に乗り込む
最初のうちはこの流れに戸惑うこともありますが、数回繰り返すだけでコツを掴めます。
また、助手席をどの程度前に出せばスムーズに乗れるのか、どの角度で足を入れるのがラクか -といった「自分なりの最適化」が自然と身についていきます。
さらに、グリップバーやサイドステップなどの後付けパーツを使えば、乗降性は劇的に改善します。特に高齢者や小柄な方には非常に効果的です。
不安になる人の共通点とは?
ジムニーの後部座席に関して不安を感じる方には、いくつかの共通点があります。以下のような状況に心当たりがある方は、特に「乗り降りしやすさ」が気になるかもしれません。
小さな子どもや高齢者を乗せる予定がある
→ 自分が乗るより、「同乗者の快適性」を重視したい人ほど気になりやすい傾向があります。
3ドア車に慣れていない(初めて)
→ セダンやスライドドア付きの車から乗り換える場合、構造の違いに戸惑うことも。
毎日使うメインカーとして検討している
→ 頻繁に後席の乗り降りが発生するなら、操作の手間がストレスになるケースも。
狭い駐車場や立体駐車場を使うことが多い
→ ドアの開閉スペースが限られる場面では、前席を動かす作業がやりづらくなることも。
ただし、こうした不安は、一度使ってみることで「思ったほど大変じゃなかった」と感じるケースが多いのも事実です。
逆に「これはラク!」と感じるポイントもある
意外かもしれませんが、ジムニーの後部座席について「思っていたよりラクだった」と感じているオーナーも多く存在します。
特に次のようなケースでは、ポジティブな印象を持つ方が多いようです。
乗り降りの動作が“シンプルに一連”で完結する
→ 助手席のレバー操作 → シートスライド → 乗車という流れがスムーズで、体が覚えてしまえば時短にもつながります。
助手席を前に倒すと「通路が意外と広くなる」
→ 助手席のスライド幅がしっかり確保されているため、想像よりもスペースに余裕があります。
「後席に乗せる頻度が少ない」場合、気にならない
→ 日常的に1〜2人乗車がメインであれば、後席の使い勝手はむしろ「+αの安心感」になります。
カスタムや工夫で乗降性を向上させている
→ 例えば、社外グリップの取り付け、ステップの追加、フラット化などによって「自分仕様の快適さ」を作り上げているオーナーも。
ジムニーは「使いこなす楽しさ」のあるクルマです。
だからこそ、「ちょっと手間がある分、愛着が湧く」という声も多いのです。
【筆者の使い方】
子供が成長し、筆者と家内しか乗らないので、常に「2シーター状態」です。リアシートを倒してフルフラットにして、ラゲッジスペース(荷物のせ)にしています。それはそれで、楽しいですよ。
不安は「慣れと工夫」で乗り越えられる
JB64ジムニーの後部座席は、確かにセダンやファミリーカーのような「万人向けの使いやすさ」はありません。
しかし、それを上回る魅力や使いこなしの楽しさが存在します。
不安を感じている方は、ぜひ一度「実際に乗り降りしてみること」をおすすめします。
そして、少しずつ慣れながら、自分なりの工夫を積み重ねていけば、きっとジムニーライフをもっと快適に、もっと楽しく感じられるはずです。
JB64ジムニーの後部座席、こう乗り降りする!【手順】
JB64ジムニーの後部座席に乗り込むには、助手席を前に倒す必要があります。
これは3ドア特有の構造によるもので、初めての方にとっては少し戸惑うポイントかもしれません。
しかし、一度流れを覚えてしまえば意外とスムーズに行えます。
ここでは、実際の操作手順を4ステップに分けて、分かりやすく解説していきます。
①助手席のレバーを引く
まず最初に行うのが、助手席シートのレバー操作です。
助手席の背もたれ横にあるレバーを引くと、シート全体が前方に倒れる仕組みになっています。
このレバーは力を入れなくても軽く引ける設計になっており、片手でも操作可能です。
初めての場合は位置を探すのに少し時間がかかるかもしれませんが、一度覚えてしまえば簡単です。
②シートを前に倒す&スライドさせる
レバーを引いたら、次にシート全体を前に倒します。
この動作によって、後部座席へ向かう通路が確保されます。
さらに、シートはレールに沿って前方にスライド可能なので、できるだけ前に動かしておくことで、足元に余裕が生まれます。
特に足元スペースを広く取ることが、スムーズな乗り込みのコツです。
✅ ワンポイント
助手席のヘッドレストが高くなっていると、前に倒した際にフロントガラスやダッシュボードに干渉する場合があります。事前に少し下げておくと安心です。
③後部座席に乗り込む(or降りる)ときの注意点
乗り込むときには、足元の段差と天井の高さに注意が必要です。
ジムニーは最低地上高が高く、乗車位置もやや高めに設計されているため、踏み込みが浅いとバランスを崩しやすいのです。
特にお子さまや高齢の方の場合は、サイドステップやグリップの追加が非常に効果的です。
また、ドア開口部の幅が限られているため、身体を一度横に向けてから乗り込むとスムーズに入れます。
このあたりは実際に何度か試してみると、自然に自分なりのスタイルが見つかるはずです。
⚠️ 注意ポイント
雨天時や砂利道では、乗り降り時に足元が滑りやすくなるので、特に注意が必要です。
④戻すときの動作も意外とコツあり
後部座席に人が乗った状態で助手席を戻す場合、足や荷物の位置を確認してからシートを戻すことが大切です。
特に、助手席の背もたれが後方に倒れる動きに注意しないと、後席の人の足を挟んでしまうこともあります。
また、ジムニーは助手席を元の位置に戻した際に“スライド前の位置に自動で戻らない”仕様なので、
適切な位置に再調整する手間が発生します。これを面倒に感じるか、逆に「自分で好きな位置に設定できる」と捉えるかは、ユーザー次第です。
🔧 補足:助手席を戻したあと、背もたれの角度と前後位置は一度座って微調整するのが理想です。
乗り降りは「流れ」と「工夫」で快適に
JB64ジムニーの後部座席への乗り降りは、たしかに一見手間がかかるように感じます。
しかし、手順を理解し、動作の流れを自然に体で覚えるようになると、むしろ軽快に使いこなせるようになります。
また、必要に応じてサポートグッズを取り入れることで、年齢や体格を問わず、快適に使えるようにカスタマイズすることも可能です。
次章では、こうした「ちょっとラクになるコツ」や「便利なグッズ類」についても詳しく紹介していきます。
JB64ジムニー乗り降りのコツと“ちょい楽”テクニック集
「ジムニーの後部座席って、どうやってラクに乗り降りするの?」
そんな疑問をお持ちの方に向けて、ここではちょっとしたコツや実際に役立つテクニック・グッズをまとめてご紹介します。
特に「家族で使いたい」「子どもや年配の方を乗せたい」という方には、“安全かつスムーズな乗降”がとても重要なポイントです。
実際の使い勝手を向上させるためのヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。
乗り降りは「順番」でスムーズに変わる
ジムニーの後部座席に乗り込むとき、動作の“順番”を意識するだけで、格段にスムーズになります。
よくあるパターンは以下のような流れです。
▶乗り込み時のおすすめ順序:
- 助手席の背もたれレバーを引く
- シートを前方に倒し、スライドさせる
- 後部座席に乗る人が乗り込む
- 助手席を戻す(必要に応じて)
ここでのポイントは、助手席を完全に前にスライドさせること。
半端にしか倒していないと、足元が狭く、体の向きが変えにくくなります。
また、乗る人が先に片足だけ入れてから体を斜めに回すと、腰の位置をスムーズに運びやすくなります。
これは、小柄な方やスカート着用の方でも使いやすい“ちょいテク”です。
子どもやお年寄りが乗るときの補助グッズ
ジムニーは最低地上高が高いため、地面からシートまでの距離が他車種よりも大きめです。
このため、特に子どもや高齢者にとっては「乗るまでの段差」が大きな壁になりがちです。
そこで役立つのが以下のようなアイテムたちです。
サイドステップ(固定式・折りたたみ式)
→ 足をかける段差ができることで、無理なく乗降できるようになります。
車内用グラブバー(アシストグリップ)
→ 握る場所があることで、バランスを崩さずに安心して乗り込めます。後部用グリップも追加可能。
携帯型ステップ(簡易踏み台)
→ 小さな子ども用に車外に置いて使うタイプ。軽量&折りたたみ式が便利。
スライド補助マット or 回転シートカバー
→ 車内での動作補助としても有効。特に高齢者の「腰を回す動作」をサポートしてくれます。
🛠 Amazonや楽天でも「ジムニー用アシストグリップ」「サイドステップ」などの専用品が多数ラインナップされています。
助手席を使った“裏ワザ”乗降法
実は、ジムニーオーナーの中には「こんな乗り方をしている」というちょっとした裏技的な方法を使っている方もいます。
たとえば…
助手席に座っていた人が一度降りて、後席の人を先に乗せる
→ 狭い場所でもゆとりを持って乗り込める方法。ファミリーユースにおすすめです。
助手席を完全にスライドさせたあと、“シートを起こさずに”後部へ回り込む
→ シートが前に倒れている状態をキープすることで、戻す手間が省ける場面も。
後部座席側の荷室ドアから先に荷物だけ積む→その後に乗車
→ 荷物と人の動線を分けることでスムーズに。
こういった小技は、車に慣れてくるほど自然と身につく“ジムニー流の知恵”と言えます。
よくある「やりがちミス」とその回避法
後部座席の乗り降りで、意外と多いのが“ちょっとした操作ミス”や“気配り不足”によるトラブルです。
以下によくあるパターンとその対策をまとめておきます。
| やりがちなミス | 回避方法 |
|---|---|
| 助手席を倒すときにレバー操作を忘れる | シート横のレバーの位置を事前に確認しておく |
| シートが最後まで前に出ていない | スライドが途中で止まりがち。しっかり前に動かす |
| 足元の段差に気づかずバランスを崩す | ステップ追加+先に片足を入れて体の向きを変える |
| 助手席を急に戻してしまい後席の人が驚く | 声かけや足元確認をしてから戻すのが基本 |
| 荷物を先に積んでスペースが狭くなる | 人→荷物の順にすることで乗りやすくなる |
特に家族での利用やアウトドアシーンでは、こうした細かい気配りが“快適さ”に大きく影響してきます。
一度失敗して覚えるのも経験ですが、あらかじめ知っておくだけで、かなりスムーズに動けるようになります。
ジムニーの乗り降りは「ちょっとした工夫」で快適になる
JB64ジムニーの後部座席は、一般的な車と比べて“クセ”のある構造です。
しかし、そのクセを理解し、ちょっとした順番・姿勢・グッズの工夫を取り入れるだけで、乗り降りは格段にスムーズになります。
「慣れ」と「工夫」は、ジムニーを楽しむ上での大事な要素です。
ぜひあなたのスタイルに合った“ちょい楽テク”を見つけて、より快適なジムニーライフを手に入れてください。
【筆者の思い出】
1986年頃の彼女(現在カミさん)の愛車を思い出しました。「ホンダ City」です。Cityは3ドアで後部座席に乗るには前席のシートを前に倒さなくてはなりません。ジムニーは(後部座席乗り降りに関して)似てます。昔、そういった経験をしているから、ジムニーは違和感ありませんでした。筆者のように、過去「3ドア車」を経験したことがある方には違和感がないでしょう。
JB64ジムニー後部座席の乗り心地、リアルな声はどう?

身長173cmだと収納ネットがかなり近い!
足元&座り心地はちょっとハードめ。
リアシートはめったに座らないので新鮮。
JB64ジムニーの後部座席に対して、「狭そう」「固そう」「長時間乗るのはキツいのでは?」といった不安を感じている方は少なくありません。
とくにファミリーカーやミニバンなどに慣れている方からすると、乗り心地の快適さに物足りなさを感じる場面もあるかもしれません。
しかし、実際に乗ってみると「思ったより悪くない」「体格によっては意外と快適」という声も多く、使い方や工夫によって印象が大きく変わるのがジムニーの特徴でもあります。
ここでは、さまざまな体格・使用シーン・視点から、リアルな乗り心地のレビューと改善ポイントをご紹介していきます。
身長185cmの人が「余裕」と言った理由
ジムニーの後部座席に対して「大柄な人には厳しいのでは?」と思われがちですが、実際には身長185cm前後の方でも“意外とイケる”という声もあります。
なぜなら、JB64は見た目以上に天井が高く、頭上空間に余裕があるからです。
直立姿勢に近いシート角度も相まって、「圧迫感が少なく、思ったよりも窮屈さを感じない」というのがその理由です。
もちろん、足元スペースはややタイトですが、前席をやや前方にスライドさせておけば、大柄な方でも足を組める程度の余裕は確保できます。
✅ ポイント
身長よりも「座高と足の長さ」のバランスで印象が変わるため、シート位置の調整が快適性のカギになります。
長距離ドライブではこう感じた!実体験レビュー
後部座席に乗って長距離移動をした際のレビューとしては、「静粛性」と「振動吸収性」が快適性に直結するポイントだと感じました。
JB64ジムニーはラダーフレーム構造+リジッドアクスルサスペンションという本格オフローダー設計のため、
舗装路での乗り心地は一般的な乗用車とはやや異なります。
- アスファルトの継ぎ目では“コツン”という硬さを感じやすい
- 長時間乗っていると、お尻まわりに疲労感が出ることも
- 静粛性はやや劣るが、会話は普通にできるレベル
とはいえ、シートクッションを追加したり、遮音マットを使うことで改善可能です。
車中泊やキャンプ帰りの高速移動でも「ちょっとした工夫でだいぶ変わる」と実感しました。
カーブや段差で感じる“ジムニー特有のクセ”
ジムニーは高い走破性を備える一方で、オンロードでの挙動には“クセ”を感じる場面もあります。
特に後部座席では、次のような印象を持つ方が多いです。
カーブでややロール(横揺れ)を感じやすい
→ 高めの車高とフレーム構造が影響。体が左右に振られやすい傾向があります。
段差での“突き上げ感”がダイレクトに伝わる
→ サスペンションの硬さが原因。後部座席は特に顕著です。
後輪の真上に座る感覚がある
→ タイヤからの入力がダイレクトに伝わりやすいため、悪路や未舗装路では「オフローダーらしさ」がむしろ魅力にも。
このようなクセは、運転スタイルやシチュエーションに合わせて「ゆっくり丁寧に走る」ことを心がけるだけでも大きく緩和されます。
✅ 対策アイデア
背もたれにクッションを挟む/乗車位置を中央寄りにする/手すりを活用して安定姿勢を取る、など。
JB64ジムニーの後部座席リクライニング
純正のジムニーJB64は左右独立してリクライニングできますが、後部座席のリクライニング角度が浅く、ほぼ直角に近い状態です。
これが「後席に長時間乗ると疲れる」と言われる大きな要因のひとつです。
気になる方は、シートクッションなどを使いましょう。
ジムニー後部座席の乗り心地は「クセあり+工夫で快適」
JB64ジムニーの後部座席は、「クセがあるが、対処可能」というのが正直なところです。
乗り心地はやや硬めで、体への負担もゼロではありませんが、体格・工夫・カスタム次第で印象は大きく変わります。
とくに、家族や友人を乗せる機会がある方は、ちょっとした改善グッズや姿勢の工夫を取り入れることで、より快適なジムニーライフが実現できるはずです。
次のセクションでは、実際に「どんなアイテムでデメリットを潰せるのか」をご紹介していきます。
JB64ジムニーのデメリットを潰す!おすすめカスタム&便利グッズ
JB64ジムニーは、走破性やデザイン性に優れた魅力的なクルマですが、実用面では「惜しい」と感じるポイントも少なくありません。
特に後部座席まわりや乗り心地、収納性に関しては、日常使用の中で「あともう一歩」の場面に出くわすことがあります。
しかし、そこはジムニー。
ちょっとしたカスタムやグッズの導入で、デメリットをしっかり補えるのがこの車の面白さでもあります。
ここでは、ジムニーオーナーの実体験をもとに、「これは本当に買ってよかった!」と実感できる便利アイテムやカスタム例をカテゴリ別にご紹介していきます。
乗降サポート系:グリップ・ステップ・アシストバー
ジムニーの車高は軽自動車の中でも高めに設定されているため、乗り降りに手間を感じる方が少なくありません。
特にお子さまやご高齢の方にとっては、「ちょっと乗りにくい」と感じることもあるでしょう。
そんな場面で活躍するのが、以下のようなサポート系アイテムです。
サイドステップ(固定式/可倒式)
→ 足のかかりができることで、踏み込みやすさが大きく向上。デザイン性の高い社外パーツも豊富です。
アシストグリップ(助手席・後部座席)
→ 握れる場所があることで、乗降時のバランスが取りやすくなります。ネジ一本で取り付けられる簡易タイプも人気。
乗り心地改善:クッション・背当て・断熱サンシェード
ジムニーの乗り心地は、ラダーフレーム構造の恩恵もあり「硬めでしっかり」とした印象。
しかし長時間のドライブや街乗りでは、腰やお尻に負担を感じるという声も多く聞かれます。
そこで導入したいのが以下のような快適性向上アイテムです。
低反発ゲルクッション/腰サポート背当て
→ 長距離運転時の疲労軽減に効果的。特に後部座席には追加で置くだけのタイプが便利です。
断熱サンシェード(車種専用設計)
→ 夏は強烈な日差しを遮り、冬は車内の保温力をアップ。車中泊時にも活躍します。
静音・断熱フロアマット
→ ノイズや熱の伝達を軽減。体感レベルで静かになります。
荷室活用&車中泊カスタム:シートアレンジと床マット
JB64ジムニーは、後部座席を倒すことである程度の荷室空間を確保できますが、完全フラットにはならず段差が残るのが悩みどころ。
車中泊やアウトドア用途での活用を考えるなら、以下のようなアイテムがあると非常に便利です。
ラゲッジフラットマット/ベッドキット
→ シートの段差を埋めてフラットな空間を確保。車中泊派の必須アイテム。
防水ラゲッジマット(滑り止め付き)
→ アウトドア用品や濡れた荷物も気にせず積める。お手入れも簡単。
収納ボックス・積載棚カスタム
→ 狭い室内を収納ボックスで有効活用しましょう。
カーテン・シェード類
→ プライバシー確保と断熱効果を両立。マグネット式が便利です。
買ってよかった!オーナーが本気で推す神アイテム3選
ここでは、ジムニーオーナーたちの間で「本当に買ってよかった!」と評判の高い定番人気アイテム3選をご紹介します。
【1】アシストグリップ(助手席・後部用)
握りやすさと剛性があり、ジムニーの無骨な内装ともマッチ。DIYで取り付け可能な点も◎。
【2】ラゲッジフラットデッキ
段差を吸収してフルフラットな荷室空間を実現。車中泊・長尺物の積載がラクになる名アイテム。
【3】ジムニー専用サンシェードセット
夏・冬ともに快適性がグッと上がる人気アイテム。専用設計でフィット感抜群です。
✅これらは「快適性」「実用性」「見た目」すべてを底上げする“投資効果の高いグッズ”として非常におすすめです。
ちょっとしたアイテムで、ジムニーはもっと快適になる
JB64ジムニーは、その無骨な魅力と走破性が最大の武器ですが、使い勝手の面では「あと少し」と感じるポイントもあるのが正直なところです。
ですが、そこを自分好みにカスタムして“乗りこなしていく”楽しさこそが、ジムニーライフの醍醐味でもあります。
この記事で紹介したような便利グッズや改善アイテムを取り入れることで、
「不便」→「快適」に、「不満」→「満足」に変えていくことができます。
次は「ジムニーを選んでよかった」と実感できるポイントを、リアルな声とともに紹介していきます。
「JB64ジムニーにしてよかった」理由は、やっぱりコレ
後部座席の使い勝手や、3ドア構造による乗り降りのしづらさ。
たしかにJB64ジムニーには、万人向けとは言えないポイントが存在します。
それでも多くの人がジムニーを選び、「やっぱりジムニーにしてよかった」と感じているのは、それを上回る“魅力”と“満足感”があるからです。
ここでは、実際のオーナーの声や体験をもとに、ジムニーがなぜこれほどまでに愛され続けるのかを探っていきます。
「後部座席がちょっと不便」でも選ばれる魅力
ジムニーはあくまで“運転すること”や“アウトドアユース”を主軸に置いたクルマです。
そのため、後部座席の広さや乗降性といった“快適性のすべて”を求める方には、正直に言えば不向きかもしれません。
それでもなお選ばれる理由は、以下のようなポイントに集約されます。
デザインと個性の強さ
→ 他にない独特なスクエアフォルム。見た瞬間に「カッコいい」と感じる人も多く、所有欲をくすぐります。
本格的な悪路走破性能
→ 軽自動車でありながら、ラダーフレーム&パートタイム4WDを備えた“本物”のオフローダー。
カスタムによって個性が広がる
→ 不便さを楽しみに変える「育てる楽しさ」がある。
つまり、ジムニーは「後部座席が少し不便」であっても、その全体としての“味わい”や“遊び心”が、それを帳消しにしてしまうほど魅力的なのです。
むしろ“3ドアが良い”という声もある
多くのユーザーが最初に抱く「3ドアで後部座席が使いにくそう」という印象。
しかし、乗り始めてみると逆に「3ドアだからこその魅力がある」と感じる人も少なくありません。
ボディが短くて取り回しがしやすい
→ 狭い道や駐車場での取り回しは、むしろ5ドアよりも優秀。
無骨でシンプルな“道具感”がかっこいい
→ 余計なラインや機能がなく、逆に“潔さ”を感じるという声も。
後席の“特別感”がある
→ 子どもが「秘密基地みたい」と喜んだり、あえて不便さを楽しむという遊び心も◎
3ドアは確かに制限もありますが、その制限を個性として受け入れられるかどうかが、ジムニーとの相性を決めるカギなのかもしれません。
ジムニーがくれる“所有する楽しさ”って?
ジムニーの最大の魅力は、“乗ること”だけでなく“所有すること自体が楽しい”という点にあります。
- 洗車するたびに「やっぱりカッコいいな」と見惚れる
- カスタムパーツを探している時間が楽しい
- 少し不便でも「まあそれもジムニーだから」と笑える
- 他のジムニーとすれ違うと、自然と挨拶したくなる
こうした“感情が動く瞬間”が、ジムニーにはたくさん詰まっています。
さらに、SNSやYouTubeでのジムニーコミュニティも活発で、「情報を共有しながら育てていける」というクルマ以上の存在になっていると感じるユーザーも多いようです。
ジムニーは、ただの移動手段ではなく、ライフスタイルそのものを豊かにしてくれるパートナー。
その魅力は数字では測れない、“所有感と愛着”にこそ宿っているのです。
よくある質問 FAQ【JB64ジムニー後部座席編】
ここまで読んでも「やっぱり不安…」「こういう場合どうなの?」と感じる方もいるかもしれません。
そこで最後に、よくある質問をFAQ形式でまとめました。あなたの疑問がここでスッキリ解消されるはずです!
1. ジムニーの後部座席って、大人が乗るには狭すぎますか?
A. 正直、広くはありません。ただ「短距離移動や非常時の4人乗車」なら問題なしという声が多いです。前席の位置を工夫すれば、大人でも十分座れますよ。
2. 「3ドア車」の乗り降り、やっぱり面倒ですか?
A. 最初は少し手間取りますが、慣れればスムーズになります。助手席を倒して乗り込む一連の流れは、数回で体が覚えます。補助グリップやステップを付けるとさらにラクに。
3. 子どもや高齢の方にはキツい?対策はある?
A. たしかに段差が高くて乗りづらい場合がありますが、サイドステップやアシストグリップを追加することでかなり快適になります。実際、家族で使っているユーザーも多いです。
4. ジムニーの後部座席、リクライニングできないの?
A. 純正で左右独立してリクライニング可能です。ただし、グレードによる違いがあります。
5. 長距離ドライブで後部座席はツラくない?
A. クッションを追加したり、遮音・静音アイテムを使えばかなり改善されます。標準状態ではやや硬めなので、長時間乗るなら対策はしたほうが快適です。
6. 荷室から乗り降りってできる?裏ワザ的に?
A. 荷室ドアから後部座席にアクセスするのは一応可能ですが、荷物があると難しいです。非常時や工夫次第では使える“裏ルート”として覚えておくと便利かも。
ちなみに、ノーマルのままでは車内からリアのドア(ハッチ)は開けられません。
7. 正直、ジムニーの後部座席って「アリ」なの?「ナシ」なの?
A. 「アリ」か「ナシ」かは使い方次第です。メインで人を乗せる用途だと不便かもしれませんが、2人乗りメイン+たまに使うなら十分“アリ”です。不便さを楽しめるなら、むしろ愛着が湧くはずです!
ちなみに、筆者は後部座席は常にフラットにして、ラゲッジスペースにしてます。乗るのは、私と家内の2人がメインだからです。ほぼ2シーター状態ですね。
ジムニー後部座席の乗り降りについてポイントまとめ
この記事で解説した要点を下記にまとめました。
- ジムニー後部座席の乗り降りは助手席を倒す必要がある
- 3ドア構造ゆえに乗降性にはワンクッション多い
- 足元スペースはやや狭めだが慣れで対応可能
- ヘッドクリアランスは高く圧迫感は少ない
- 高齢者や子どもにはステップやグリップの追加が有効
- 助手席を完全に前に出せば通路は意外と広い
- 乗るときは“片足→回転”の順がスムーズ
- 戻すときの助手席操作にも小さなコツがある
- 雨の日や砂利道では滑りやすく注意が必要
- カスタム次第で乗り降りの快適さは大きく向上する
- 静音化やクッション追加で乗り心地も改善可能
- ジムニー後部座席はリクライニング可能
- 「後席に頻繁に乗せない」使い方なら十分実用的
- 不便さを楽しめる人には“育てがい”のある一台
- ジムニー後部座席の乗り降りは“理解と工夫”で快適になる
JB64ジムニーの後部座席に不安を感じている方も多いでしょう。
ですが、そうした不便さも含めて「ジムニーらしさ」だと捉えることで、このクルマとの付き合い方は驚くほど前向きに変わります。
「ジムニーにしてよかった」と語るオーナーたちの多くが口にするのは
“乗るたびに、所有していること自体がうれしくなる”という感覚です。
筆者もそうです。
ドアロックを解除して乗り込むたびに、エンジンをかけるたびにワクワクします。
「今日は、どこに行こうか?相棒!」って感じです。
もしあなたが、ちょっとしたクセも愛せるクルマを探しているなら…
ジムニーは、最高の相棒になってくれるクルマですよ。
.
ひょっとして、今の車を手放すことをご検討中ですか?
であれば、「車選びドットコム」の一括査定サービスを試してみるのもアリです。
複数の買取店に一括で見積もり依頼ができて、手続きもスマホで簡単・無料。
私自身も、家族の車を売却する際に「いちいち店を回らなくて済む」のが非常に便利だと感じました。
🚗 買取価格を比較して納得したい人や「とりあえず相場だけ知りたい」という方にもぴったりです。
.
🚗 「今すぐ乗りたい」「納車を待ちたくない」という方は…?
そんな時は、カーリースで“即納車両”を探すのもひとつの手です。
納期のかかる新車購入とは違い、カーリースなら「即納モデル」も豊富に選べます。
.
🚗「納車まで長く待つのは嫌」「すぐに手に入る車が欲しい」
そんな悩みをお持ちの方へ。新鮮在庫の中から、今すぐ乗れるクルマを見つけませんか?
.
🚙この記事を書いた人
【四駆SUV研究調査室:室長/Webライター:緒方智幸(むらなす)】
熊本在住。阿蘇の大自然と、愛車スズキ・ジムニーJB64(2023年式)を愛してやまない現役オーナーライターです。
「40年超・無事故」のキャリアに基づく安全運転の真髄を、ブログとYouTubeで発信中。
記事はすべて、自らの実体験、ユーザー取材、そしてプロの整備士への徹底したヒアリングを元に構成しています。
🎥 四駆SUV研究調査室 YouTube公式サイト
40年無事故のプロが実践する「SUV特有の運転のコツ」や「スマートな所作」を映像で分かりやすく解説しています。 「セルフ給油の極意」など、初心者からベテランまで役立つ動画を配信中!
👉 四駆SUV研究調査室公式YouTubeチャンネルはこちら
——————–
🏍 バイク専門ブログ『むらなす式バイクスタイル』も運営中。
1984年から続く40年以上のバイクライフに基づく、安全で楽しいライディングの知恵を公開しています。
👉 ブログ「むらなす式バイクスタイル」はこちら
ジムニー後部座席シートベルトの外し方が分かりませんか?この記事の動画と図解で解決できますよ!
⬇️
👉【図解と動画で完全解説】ジムニー後部座席シートベルトの外し方|ボタンがない原因と解除のコツ
🚙 「ジムニーのスペアタイヤって外していいの?」答えはこちらをご覧ください!
⬇️
👉ジムニーのスペアタイヤを外す【真実】をJB64現役オーナーが徹底解説!後悔しないための全知識
走行時間のリセット方法はこちらの記事をご覧ください!
⬇️
【画像で解説】ジムニーの走行時間リセット方法|JB64/JB74対応&他スズキ車にも応用可!